肝臓がんのステージを生きる
肝臓がんを治したい・改善したい人のための情報サイト
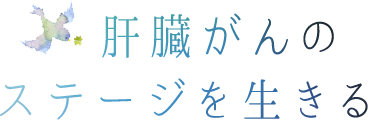
肝臓がんを治したい・改善したい人のための情報サイト
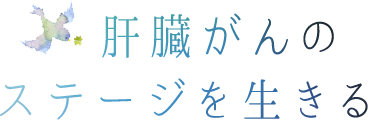

肝臓がんに対する知識を深め、
前向きに生きるための情報サイト
初期の自覚症状がほとんどないと言われる肝臓がん。気づいた時にはすでに転移しており、切除さえできないケースも少なくありません。しかし、標準治療をはじめ、それを補完する代替療法の研究も進んでおり、治療の望みは以前より大きいと言えます。このサイトでは、肝臓がんの症状・ステージのほか、各種治療法や再発予防について、さらに治療中や予後における生活の質(QOL、クオリティ・オブ・ライフ)を高めるための考え方などを紹介しています。
肝臓の根治やQOL維持のために
重要な指針となるステージ分類
多くのがんには、病状の進行度合いによって「ステージ」と呼ばれる段階が定義されています。ステージ1が初期段階で、ステージの数字が上がるごとに重症化していると判断できます。ステージによって、治癒や再発の可能性を予測することができるので、治療方針の決定に使われます。
初期段階のがんだが、油断は禁物
転位が見られない初期段階であるにもかかわらず、5年生存率は54.6%と決して高い数字ではありません。この段階では自覚症状がほとんどなく、定期健診で見つかるケースがほとんど。治療方法としては、「切除手術」をはじめ、「エタノール注入」「ラジオ派焼却」といった局所療法が用いられます。
ジワジワと進行しているのに気づけない
5年生存率は43.1%と約半分以下となり、治療の難しさを物語っています。自覚症状はまだ乏しいものの、人によっては食欲不振や全身の倦怠感を感じる場合も。治療はステージ1と同様、適応があれば「切除手術」、その他は「エタノール注入」「ラジオ派焼却」などが行われます。
他の器官への転移が懸念される状態
腫瘍が筋肉の層などを越えて広がっている状態。5年生存率は24.8%となり、腹水や黄疸などの症状がでることもあります。治療においては医師から「手術が難しい」と宣告されることがあり、代わりに肝臓の動脈を塞ぎ、がん細胞への栄養を遮断する「肝動脈塞栓術」が用いられます。
治療が困難な肝臓がんの最終段階
リンパ節や、離れた他の臓器に転移している状態。この段階では、腹水や黄疸などの合併症があるほか、遠隔転移がある場合は吐血、呼吸困難などの苦痛を伴うことがあります。5年生存率は10%以下となり、治療としては「肝動脈塞栓術」や「化学療法」、症状によっては「放射線治療」などが行われます。
「ステージ分類」と合わせて
肝臓がんの治療方針を定める指針
肝臓がんの治療方針を決めるのは、症状の進行度合いを評価した「ステージ分類」だけではありません。肝臓は、体の中でも極めて重要な働きを担う器官であることから、ステージ分類のほかに「肝機能がどのくらい保たれているか」もチェックされることになります。それが「肝障害度分類」です。
評価方法は、日本肝癌研究会がまとめた「肝障害度分類」と、欧米で主流となっている「Child-Pugh分類」の2つ。それぞれの評価基準や内容をはじめ、適用される治療法までを分かりやすく解説します。

がん以外に患者を苦しめる症状が…
肝臓がんに限らず、がんが進行すると合併症と呼ばれる症状が現れはじめます。肝臓がんの場合は、腹水や胸水、黄疸、肝性脳症、肝腎症候群、門脈圧亢進症などがその代表。合併症は治療可能なものもありますが、肝臓がんを患っている限りは、このリスクから逃れることはできません。また治療だけでなく、緩和ケアが必要です。
腹水は、腹部の臓器と臓器の間にあたる「腹腔」と呼ばれる部分に水がたまってしまう症状です。ここに水がたまることで、カエルのようなお腹になるのが特徴です。
肌や目、尿などの色が黄色く濁る症状。肝機能の低下により胆汁がうまく流せなくなることで、血中に黄色い色素が増え、そのまま沈着することで発生します。
肝臓の機能低下により、血液中の毒物を除去しきれず、脳に悪影響を及ぼすことによって起こる合併症。進行すると意識を消失する「昏睡」に至ります。
肝疾患により引き起こされた急性腎不全を指します。発症すると尿の量が非常に少なくなるのが特徴で、老廃物が排出できず、昏睡状態に陥る危険があります。
臓を通る血管である、門脈の異常によって起きる病気。門脈の圧が上がることで、やがて静脈が破れ大出血を起こしたり、「肝性脳症」につながる恐れがあります。
肝臓がんに伴う合併症には、癌性疼痛や消化器症状など、他にも多くの種類があります。周囲の人は、患者をサポートするための方法を講じる必要があります。
がんのステージや臓器の障害度に
応じた治療があります
肝臓がんの治療効果を高めるためには、定期検診や早期発見が非常に重要なポイントとなります。実際に罹患が確認された場合には、一体どのような治療法が採用されることになるのでしょうか?病状や進行度合いによっては適用できなくなる治療法もありますので、注意が必要です。
最も確実な治療法とされるが
臓器に対する影響が大きい
肝臓がんの治療法の中でも、いちばん優先されるのが、がん細胞の摘出手術です。肝臓を蝕み、肝機能を著しく低下させている病巣をまるごと切り取るため、他の治療法より確実性が高い反面、身体への負担も大きい方法。また再発率が高い肝臓がんの場合、手術が適用されないケースも多いと言われています。
機能が低下した肝硬変の場合の選択肢
ただし転移がない場合に限られる
がん細胞に侵されていない正常な肝臓を移植する方法。以前はどうしても助からない小児肝臓がんなどに適用されていましたが、近年は成人に適用されることもあります。肝臓がんの治療法の中でも、費用・リスクともに大きい方法として知られています。このため、適用できない患者も多くいます。
エタノールの化学作用でがんを死滅
比較的安全で簡便な治療法
肝臓がんの切除手術ができない場合に、局所的に治療を施してがん細胞を死滅させる手法です。患部にエタノールを注入し、たんぱく質を凝固させる化学作用によってがん細胞を死滅させます。比較的安全で簡便な方法としても知られており、肝臓がん治療においては、長きに渡り重用されてきました。
高周波の電磁波をあててがんを凝固
初期段階の肝臓がん患者に有効
局所療法のひとつで、電子レンジにも使われるマイクロ波を使って、高熱でがん細胞を凝固・死滅させる方法。適用できる範囲はそれほど大きくないので、患部の比較的小さい早期肝臓がんに有効な方法とされています。腫瘍が大きければ、数回の照射で治療をします。腫瘍が複数あった場合でも適応されます。
ラジオ波による熱でがんを焼却
肝機能障害などの合併症が起こる懸念も
局所療法のひとつで、マイクロ波と同じメカニズムを持ちますが、その威力は高く、治療回数も少なくて済むのが特徴と言えます。費用も保険適用となっています。ただし、デメリットもないわけではありません。肝臓への負担は少ないものの、肝臓の近くにある臓器に影響してしまう可能性があるのです。
栄養を運ぶ血管を人工的に防ぎ
がんを兵糧攻めにする治療法
肝臓がんの治療にあたり、切除など外科的治療法が難しい場合に用いられる方法のひとつです。動脈をふさぎ、がん細胞に栄養が運ばれるのを遮断することで、壊死させます。特に初期以降の肝臓がん患者に対し適用され、近年は医療現場で数多く採用されています。
抗がん剤を全身に巡らせがんを攻撃
標準治療だが副作用が懸念
静脈注射や点滴などで、全身に化学薬品を巡らせ、がん細胞を攻撃していく治療法。肝臓以外のがんにも広く適用されている、スタンダードな治療法のひとつです。一定の効果が期待できるものの、その副作用の強さを心配する声が挙がるのも事実。患者やその家族は、ケア法を考えていく必要があります。
外部から放射線をあてて肝細胞を死滅
体力の少ない高齢者にも適応される
効果はあるものの、周辺組織へのダメージが心配されたため、肝臓がんにはあまり適用されてこなかった治療法です。しかし近年、医療技術に進歩が見られるようになりました。脳の病気に用いられてきた放射線治療の効果が認められ、その他の器官にも応用されるようになってきたのです。今後に期待したい治療法です。
がん細胞の遺伝子に作用する
注目を集める最新がん治療法
正常な細胞にダメージを与えず、がん細胞のみに作用する遺伝子を投与する治療法。抗がん剤や手術などの治療方法と併用することが可能です。外科治療・放射線治療・化学療法の三大がん治療に比べて実績はまだ少ないですが、近年では大学病院などで多くの治験が実施され、最新のがん治療として注目を集めています。
がん組織に狙いをさだめ
ピンポイントで放射線を照射
重粒子線治療は、がん病巣に向けてピンポイントで照射できる最先端の放射線治療法。体の表面では放射線量が弱く、がん病巣で放射線量がピークになる現象を利用しているので、副作用が少なく、一度の照射で高い効果が期待できる点が特徴とされています。通院で治療が可能で、体力のない方や高齢の方でも治療をうけることができます。
360度の方向から照射できる
陽子線を使った放射線治療
威力は高いものの、周囲の細胞にまでダメージを与えてしまうリスクのある従来の放射線治療とは違い、粒子が軽く、360度の方向から照射できる陽子線を使った放射線治療の1種です。がん細胞にピンポイントで照射できるため、肝機能を温存したまま治療を進めることができます。転移前の早期がんであることが治療の条件です。
リンパ球の司令塔「樹状細胞」
の働きを利用する療法
「樹状細胞にがんの目印を覚えさせる」ことでがんと戦う治療法。樹状細胞は、体内に入ってきた異物の特徴を覚え、リンパ球に伝えて攻撃命令を下すという働きを持っています。この樹状細胞にがんの目印を覚えさせることで、リンパ球が目印を持つがん細胞を狙って攻撃できるようになるという仕組みになっています。
白血球の一種「リンパ球」を
増殖させて免疫力を高める
がん細胞を攻撃する白血球の一種「リンパ球」を体外で増殖させて体内に戻し、免疫力を高める療法。ほぼすべてのがんに対応できます。自分自身のリンパ球を使うので、副作用がほとんどない点も特徴で、標準治療では副作用が強く出てしまうという場合にも適応します。一方、一部医療機関でしか治療を受けられないという点がデメリットです。
なぜ「手術が適用できない」
と判断されるのか?
手術できない場合の治療法とは?
肝臓に限らず、がん治療において「摘出手術」は多く採用されている治療法です。患部を取り除いてしまうことでがん細胞増殖を抑制し、病状の進行を食い止めることができるからです。しかしケースによっては、医師から「手術できません」と宣告されることがあります。なぜなのでしょうか?

肝臓がんの治療が思うように進められない場合
肝臓がんには自覚症状が少ないため、発見した時には、すでにかなり進行しているケースもあります。一方で、病院で提供される標準治療には適応条件があり、症状や進行度合いによっては、手術や抗がん剤治療に耐えられない患者も多くいます。そんな方のために紹介したいのが、標準治療を補完し、治療中や予後における生活の質(QOL)を高める効果が期待される代替医療です。その代表例を、体験談とともに紹介します。
最もよく利用される補完代替医療
「サプリメント・健康食品」の成分を解説
病院での標準治療をサポートする「補完代替医療」として、サプリメント・健康食品は大きな注目を集めています。「免疫力を高め、闘病に耐えうる身体を作る」「治療の副作用を抑える」などのサポート効果を期待できる成分を詳しく解説します。

世界の大学で臨床試験が行われ
54ヶ国で販売実績がある日本発の免疫成分
その名前から分かる通り、米ぬか由来の物質。日本発の特許成分ですが、すでに世界54ヶ国で使用されていて、国内外28以上の大学や病院との共同研究により、免疫を高めたり、抗がん作用があることが分かっています。また臨床試験で抗炎症作用も検証されており、抗がん剤の副作用軽減や、QOLの改善にも効果が期待されます。

古くから珍重されてきた
ブラジル原産の食用キノコ
ハラタケ属のきのこの一種で、世界各地に自生しています。アガリクスは免疫力を高めることで、がん細胞の増殖に働くと言われます。また抗がん剤の副作用を抑える働きも期待されています。しかし人体への有効性と安全性については、信頼できるデータが見当たらないという調査結果もあるようです。

肝臓を保護する作用も知られる
ウコンに含まれている成分
クルクミンは、ショウガ科の植物であるウコン(別名:ターメリック)に含まれている色素成分です。抗酸化作用や抗炎症作用など、がんの補完代替医療に役立つ働きが期待できるほか、肝臓を保護する作用もよく知られており「二日酔い防止のために、ウコンドリンクを飲んでおく」という習慣を持つ人もいます。

特に人参に含まれるサポニンの
健康効果に注目
人参サポニンは、ジンセノサイドというサポニンが主成分となっており、新陳代謝と免疫力を高める効果があります。がん細胞の撃退や、転移抑制への働きが期待されているのです。またサポニンには抗酸化作用があるため、発がん物質が遺伝子の変異を起こしてがん細胞化させることを阻害する効果も報告されています。

コンドロイチンが豊富に含まれる
海の猛者の軟骨には抗がんパワーがある?
サメは、生命力が強い魚類として知られています。怪我に対する治癒力が高く、病気にもかかりにくいのです。このため「サメの身体組織を摂り込むことが、難病の治療に役立つのではないか」という研究が進められてきました。その中で注目されたのが、軟骨。コンドロイチンという成分が豊富に含まれています。

薄毛改善だけじゃない?
ヌメリ成分・フコイダンのパワーとは
フコイダンとは、コンブやワカメなどの海藻のヌメリ成分のこと。「発毛効果がある」とされ、薄毛に悩む男性から注目されていますが、一部では「がんを撃退する効果がある」とも言われています。その根拠について調べています。

以前から結構効果が注目されてきた
プロポリスの肝臓がんに対する効果は?
ミツバチが作り出す薬効物質。その健康効果は以前から注目されており、多くの研究も進められてきました。近年は「プロポリスが肝臓の健康のために効果を発揮する」ことが分かっています。肝臓がんの予防改善にも効果的なのでしょうか?

最近の研究で健康効果が注目される
南米に自生する「神からの恵みの木」
南米に自生する植物。古代より「神からの恵みの木」とされ、珍重されてきました。また最近の研究で「抗がん作用があるのではないか」と注目を浴びています。人工栽培が難しい植物なので、大きく普及はしていません。

日本や韓国に自生するきのこの一種
抗がん作用に大きな期待が寄せられる
こちらもアガリクスと同じく、きのこの一種です、一部の地方にメシマコブが自生する日本や韓国では、その健康効果に関する研究が、何十年にも渡って続けられています。抗がん作用に大きな期待が寄せられているのです。

漢方薬として古来から珍重される
サルノコシカケ科のキノコ
メシマコブ、アガリクスと同じく、こちらもキノコの一種。梅やナラ、クヌギの古木に自生し、古木10万本に対して2~3本ほどしか生えないと言われる希少種です。キノコにはまだまだ大きな可能性が眠っていそうです。

新しい知見として注目される
「RBS米ぬか多糖体」の抗炎症作用
がんと慢性炎症との間には、疫学的な関連性が知られてきました。肝臓がんの場合、C型肝炎ウイルス感染による慢性炎症の関与が知られます。近年の研究では、この慢性炎症の抑制が、肝臓がんの再発予防につながるとの学説が打ち出され、検証が進んでいます。そこで注目されているのが免疫調整機能を持つ「RBS米ぬか多糖体」の抗炎症作用なのです。
※米ぬか多糖体免疫研究会の資料請求フォームに移動します。
※米ぬか多糖体免疫研究会の資料請求フォームに移動します。
肝臓がんは再発率が高く、たとえ根治したとしても、5年再発率は約8割にのぼります。このため、早期発見で治療が成功した人でも、常に再発の脅威にさらされる恐れがあるのです。
再発率の高さが、肝臓がんの怖いところ。患者は病院での定期検診を続けながら、必要に応じてさまざまな再発予防治療を受けることになります。
肝臓がんは、全がんの中でも死亡数が多く、5年以内に再発する割合が80%以上にのぼると言われています。では、一体どのような原因で肝臓がんが発生するのでしょうか。さまざまな可能性について調べ、情報をまとめています。
国内の多くの肝炎患者の症状が
進行すると…
日本国内で肝炎ウイルスに感染している人は多く、その数は「40人にひとり」と言われています。いったんウイルスに感染したとしても、体内で増殖せず、そのまま排除されてしまうケースもあるのですが、慢性化すると大病を引き起こす直接的な原因になります。その詳細について調査しているページです。
肝臓が小さく硬くなり、
機能も低下している状態
肝炎に感染していることに気づかず、肝細胞が破壊と再生を長期間に渡って繰り返すのを放置してしまうと、次第に肝細胞が線維化し、肝臓自体が小さく硬くなってしまいます。これが、肝硬変です。肝臓にダメージが蓄積し、機能が低下しているだけでなく、肝臓がんへ移行するリスクを孕んでいます。
ウイルス感染に
気づかないままでいると…
「HBVウイルス」の感染によって発生する肝炎です。自覚症状はほとんどなく、また症状がほとんど出ない「無症候性キャリア」の人も、数多くいるのが特徴。とは言え、慢性化すると肝臓がんの原因ともなりかねません。その感染経路には「母子感染」が影響していることもありますので、注意が必要です。
慢性化すると、高確率で
肝臓がんを引き起こしてしまう
こちらは「HCVウイルス」の感染によって発生する肝炎です。ウイルス自体の発見から30年程度しか経過しておらず、注射などの病院治療から感染した人の数も多くなっています。慢性化すると肝硬変や肝臓がんへと進行する可能性が高まりますので、誰でも一度はきちんと検査を受けておく必要があります。
アルコールの飲みすぎは、
肝臓がんを誘発する?
過度の飲酒が肝臓にダメージを与えることは、広く知られています。その代表的な症状が、アルコール性の肝炎。「お酒を飲みすぎると、肝臓をやられるよ」と言われることは多くなっていますが、その影響は、肝臓のがん化にまで及んでしまうのでしょうか?調査していますので、参考にしてください。
自分の病気は肝臓と
関係がないと思っていても…
上記以外にも、肝臓がんの原因はあります。肝臓以外の場所で発生した病気やその治療が、肝臓に悪影響を与えることがあるのです。「自分の病気は肝臓と関係がないので、肝臓がんについては問題ない」と思っていても、意外なところからリスクが高まっている危険もあるのです。

肝臓がんには大別して2種類ある
肝臓がんとひとくちに言っても、転移性肝がんと原発性肝がんの2種類に大別されます。同じ肝臓で発症するがんではありますが、両者の性質は異なるものだということを知っておく必要があるでしょう。もちろん、治療にあたっても性質の違いが影響を及ぼしてきます。肝臓がんの種類について、知識を深めていきましょう。
その名の通り、肝臓内部でがん細胞が発生している状態です。しかしひと口に肝臓と言っても、その内部にはさまざまな器官が存在しています。「原発性肝がん」の中にも、どのような種類があるのか理解しておきましょう。またその原因や症状、そして検査/診断法について紹介していますので、ぜひご一読ください。
肝臓以外の場所から、がん細胞が血流に乗って転移することで発生してしまうがんです。もともとのがんが発生している部位は人それぞれなのですが、肝臓には全身から血液が運ばれてくるため、転移が起こりやすいことで知られています。その症状や、検査/診断法について紹介していますので、ぜひ詳細をチェックしてください。
肝臓がんの治療について考えるために、ある程度は病気のことを知っておく必要があります。そこで、肝臓がんについて寄せられる「よくある質問」への回答をまとめてみました。
「どのような病気なのか」、「何を準備しておけば良いのか」など、肝臓がんについての疑問や不安を抱えている人は、各ページの内容をチェックしてください。
肝臓がんの名医が発表・解説した
注目の記事をピックアップ
肝臓がんと闘うためには、治療や医療についての知識があるに越したことはありません。ここでは、肝臓がんに対する高度な専門性を有する名医が発表・解説したもののなかから、注目の記事をピックアップしてご紹介します。
肝臓がんに関するニュース記事を厳選
肝臓がんに関する「新治療法」「生存率」など、気になるニュースを厳選してお届けします。日々研究が続けられる肝臓がんに対する臨床結果や成果などを、分かりやすく解説していますので、ぜひ参考にしてください。